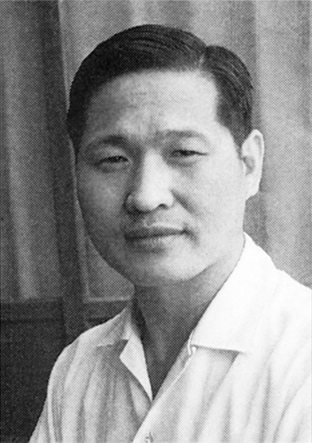第二章
戦火を逃れて南へ避難
49頁
平壌からソウルへ
不良たちに足を折られる
爆撃を避けて山道を走ったり、途中で宿泊したりで、平壌に着いたのは三日後だった。空襲から逃れて郊外に疎開している家族と合流した翌日、私は金鍾和の家を捜したが、ついに見つけることはできなかった。
その頃、韓国軍は北の人民軍に押されており、一九五〇年(昭和二五年)八月十八日には釜山に韓国政府を移していた。北の共産党政府が掌握していた平壌市内は戦勝ムードに溢れていたが、九月十五日に国連(UN)軍が人民軍の背後を突いて仁川に上陸、戦況は一変した。UN軍の進撃はすばやく、九月の下旬には、韓国軍とUN軍が平壌を制圧してしまった。
そんなある日、私は保安隊と称するチンピラの一団に取り囲まれた。地元の不良たちで北が来れば北に迎合し、南が来れば南に尾を振る連中である。
「お前は北朝鮮軍の大隊長を務めた、本物の共産党員だから殺す。死ね!」
何人かが私に飛びかかって、ハンマーで私の足を殴った。足首の骨が折れ、私は動けなくなった。運よく通りかかった韓国軍憲兵隊のジープに助けられ、留置場で調べを受けたものの、職務怠慢罪で投獄されていたことがわかり、釈放された。こんな所で殺されるのかと一時は覚悟しただけに、「まったく、人間なにが幸いするかわからない」と、思わず苦笑いをしたものだ。このとき留置場にいたなかで、重罪のある者たちは銃殺されたそうである。
戦争で町の病院はどこもまともではなかった。柔道五段だった私は、仕方なく薬局で適当な薬を捜して飲み、折れた足首には応急措置で板を縛りつけておいた。
文龍明との再会 51
十月の二十七日、金元弼と文正彬が私を尋ねて来た。文さんが出獄して、十月二十四日に平壌に到着し、私を呼んでいるので迎えに来たということだった。突然だったので、あまりにも嬉しくて言葉が出てこなかった。私はリヤカーに乗せられて、小高い所にある玉相賢*家に行ったが、文さんは喜んで迎えてくれた。その瞬間、私は文さんの手を握って泣いていた。UN軍によって興南監獄が十月十四日に解放され、自由になった文さんは、十日間歩いて平壌に来たそうだ。
玉相賢の自宅は日本式の住宅で敷地が数百坪もあり、家が何軒も建っていて、大金持ちに違いなかった。玉相賢と娘の貞愛、貞淳、文さん、金元弼、文正彬、そして私の七人が一つの家族のように生活した。一週間ほどしたら、玉相賢の夫である禹夏変の家族全員が、避難していたソウルから帰ってきたので、私たちは使っていた部屋を空けなければいけないことになった。
皆で相談したあと、西城里という所にある部屋を一つ借りることにして、そのあくる日に引っ越した。文さんと金元弼、文正彬、そして私の四人が一緒に暮らすことになった。文さんはその間、知人たちの安否を尋ねて出かけていったり、金元弼に自分の出獄を知らせる仕事をさせていた。
ところがまた、平壌では一九五〇年十二月二日、市内全域の市民に一斉に避難命令が下りた。それは、中国軍が大量に投入され、人海戦術で怒濤のように押し寄せてきたので、韓国軍とUN軍がいったん後退するしかなかったからだ。
一時は朝鮮半島の最北まで追い込まれていた北朝鮮人民軍と、それを支援する中国志願軍(十月二十五日に参戦)の前進は、予想外に早かったようである。その日は、それほど遠くない所の弾薬庫が爆撃されて一晩じゅう爆発が続き、一睡もできなかった。
家族を捨てて文に従う 52
私たちは南の方へ避難することに決めた。しかし、足のケガが治っていない私は歩けなかったので、上水口里の姉の家に自転車を取りにいき、私がそれに乗って金元弼が後ろから押していくことになった。
私たちは一九五〇年十二月四日、十時頃に平壌を出発した。季節は冬だったが、まだそんなに寒くはなかったので、避難するのに比較的障害はなかった。途中、大同郡にある私の実家に寄っていくことにした。私の家に到着すると、家族は私たちを喜んで迎えてくれた。 私が不自由な足で、こんなたいへんな時期に南へ出発することには、家族全員が「とても無理だ」と大反対した。いとこの正根は、
「お兄さんはそんな足で、どうやって南の方まで行けると思いますか」
と必死で止めようとした。文さんは、私の家族を納得させようとして、
「平壌城を目前にしたものの、北では目的が達成できなくなってしまいました。私たちは天の意
志に従い、いったん南の方まで行かなければならないのです」
と説明した。
私は獄中で交わした男の約束もあり、また文さんを再臨メシアだと信じていたので、どういうことがあっても、文さんと一緒に南の方に行かなければならないと心に決めていた。もう八十歳になっている母親に別れのあいさつをしたあと、妻に家族のことを頼んだ。そのとき、長女の孝順が出てきて、
「私もお父さんと一緒に、お父さんの世話をしながら南の方までついていく」
と涙を流したが、文さんが押しとどめた。文さんは、興南から一緒に来た文正彬にも、「後からチャンスを見て南へ来なさい」と諭して、私の家に残るよう言った。
平壌の後方には中国軍も迫って来ているので、私たちはできるだけ早く大洞江を渡らなくてはと思っていた。そこで、正根に手配してもらい、その夜のうちに船で南串面孝南里に渡ることができた。
その夜は、近くに住む姉の家に泊まった。南へ避難しようとする村人たちが大勢集まっていた。翌朝の十二月五日、姉が用意してくれた食料を自転車の後ろに積み、私が乗って金元弼が押しながら出発した。
姉は文さんを牧師だと思い、
「牧師さま、どうか私の弟をよろしくお願い致します」
と頭を下げて見送ってくれた姿が、今も生々しく残っている。(以来今日まで四十三年間、家族との音信は途絶えたまま。妻や五人の子どもはどうしているだろうか)
死ぬまで一緒と男の約束 54
南への道路は避難する人びとであふれていた。避難民たちはそれぞれに手をつないで、それこそ何万人もの人たちが、ぞろぞろと南の方へ、南の方へと歩いていた。私たちは、力浦を経て龍淵面に入り、十二時近くに加鶴里に到着した。西の方からは、爆撃機による空襲や銃撃戦の音が聞こえてきた。
その日は曇っていたので、夕日が沈んでもいないのに、日がもう暮れたようになってしまった。今日はもう進むのをあきらめ、宿を捜して休むことにしようという文さんの指示で、私たちは近くの村に寄り、入り口にある農家に入った。その家には誰も住んでいないようだった。家財道具はあったが、おそらく住人は南へ避難して行ったのだろう。台所に行ってみると、米はもちろん、キムチ、醤油、ミソなどがそのまま残っていた。
まさに人類最期の日が来たような感じだった。この世の中はこれからどうなってしまうのだろうか。家具も食料も衣料もそのままなのに、人間だけが蒸発してしまったみたいだ。
避難の途中で休むために初めて入った家の中の光景を見て、私はいろんなことを考えさせられていた。
元弼が夕食を用意して持ってきた。白いごはんに水キムチをのせた御膳である。私たちは感謝の祈りをして食事をいただいた。文さんが、
「正華は足が折れて苦労しているけれど、しばらくしたら治るだろう。また自由に歩けるようになるから安心しなさい」
と言った。そして、私が家族のことを思い出して、さみしそうに見えたのか、
「私たちは今、新しい歴史を作るために南へ行くのだ。ただ避難するための道ではない。平壌城を中心にして、新しい歴史をこの世の中に創造しようとしたが、私を監獄へ送ったためにだめになってしまった。南でもう一度やり直すのだ」と励ましてくれた。
米びつの上にきちんとたたんで乗せてあった布団をひいて横になったが、私はどうしても寝つくことができなかった。元弼は疲れていたのかすぐに寝てしまったが、文さんもなかなか寝られ
ないようだった。これからの計画でも考えているのだろうか。
「これから一生、文龍明(当時)と朴正華は苦楽をともにし、永遠に一緒に生きていこう」と獄中でお互いに誓い合ったからこそ、懐かしい故郷の村を離れ、愛している家族たち――母、そして妻と五人の子どもたち(十七歳の長男、十五歳の次男、十三歳の三男、十歳の長女、五歳の四男)――と別れて、足が折れていたけれども、ここまで来たのではないか。私の一生は
すべて、再臨メシアと信じる文さんにあずけたのだ。
やはり私も疲れていたのだろう。いつの間にか眠ってしまい、気がついたらもう朝日が昇っていた。
避難しているときの私たちの服装だが、文さんは白い絹のズボンにゴムシン(ゴム製の履物)をはき、黒いオーバーコ ートを着て、黄色い毛糸の襟巻きを帽子のようにしてかぶっていた。元弼は色あせた軍人用のズボンに運動靴のような軍人用の履物をはいて、犬の毛皮で作ったオーバーコート(日本の関東軍のもの)を着て、頭には日本植民地時代の末期を思わせる黒い色の防空頭巾をかぶっていた。まるで封建時代の婦人たちが着ていた唐衣のような感じで、顔の前の部分
だけが見えていた。彼はその外見だけでなく、女のような声をしていたので、本当に女性と錯覚するくらいだった。そして私は、作業服の上下に日本軍の靴をはいて、頭には黄色の防寒帽子をかぶっていた。
外国製の古い自転車に荷物を乗せ、足の不自由な私がまたがってハンドルを握り、元弼と文さんが交替で後ろから押していたのだが、さぞかし奇妙に見えたことだろう。
悪戦苦闘の避難行 58
南への道は幹線道路を通れれば比較的平坦で楽なのだが、アメリカ軍の憲兵があちらこちらに立って通行を制限していた。結局、避難民が通れたのは、狭くて起伏の多い脇道だけだった。日を追って避難民の数は増え、それこそ人の山のように、人の海のように、狭い道にあふれていた。南の方に行けば生き残れるという保証は何もないのに、それでも何らかの希望を持って、人びとは南へ向かっていくのである。
平壌を離れるとき、衣類や道具などをひと包みずつ背負って持ってきたが、その荷物も日が経つにつれてだんだん減っていった。歩き続けて足も痛くなり、疲れ果てているので、あまり大事でないものはどんどん捨ててしまい、避難も二十日近くになったときには、荷物はほとんどなくなっていた。
疲労のたまった身体には、真冬の寒さが強烈にこたえた。暖かい場所を求めて、草の上の雪がとけているような所をみつけては座り込み、休み休みながら進んだ。
それでも寝ぐらと食事の心配だけは、あまりなかった。
その日も、ちょっと早めに宿を捜して休むことにして、近くの村に入っていった。ある家に入ったら、相当な金持ちの家のように見えたが、誰もいなかった。やはり家財道具や食料は置いたままだった。部屋を決めてからしばらく休んだあと、元弼が夕食を用意してくれたので三人で食事をした。痛む足でこのまま南まで行けるか、私には自信がなかった。
私たちは、ますます増えていく避難民に混じって南へ向かっていた。その途中、黄州あたりに、角度がほぼ三〇度近くある急な坂があった。その坂は百五十メートルくらい続いていて、とても自転車を押しながら登れそうな道ではない。私が自転車に乗っていると、元弼がいくら努力して押しても、なかなか登ることはできなかった。ちょっと進んだかと思えばすべったりして、自転車が後ろ向きに倒れ込んでしまう。
まわりは避難民でいっぱいで、それぞれが先を争って進もうとしていた。このままではどうしても先に行けそうにないと思った私は、私のために文さんも元弼も南へ行けなくなるのでは申しわけないので、文さんに言った。
「私はもうだめです。私を置いて先に行ってください。私はここで何とかがんばりますから。たとえどうなろうとも、私は私の運命に従います」
すると文さんは怒って、「お前と私は死ぬまで一緒だと約束したではないか。今後どんなことがあっても、神を信じていこう。心配するな」
と言い、元弼に自転車を引かせ、私を背負って坂を登ってくれた。感激した私は、文さんを信じてついていくことを改めて誓った。
やっとソウルへ辿りついたが 60
私たち三人はその後、南への避難民に共産軍が混じっているという情報による、UN軍の戦闘機の機銃掃射で大勢が死ぬ恐怖に遭ったり、虱に悩まされたりの難道中を乗り越え、沙里院、下城、東海州、青丹、内城、龍媒島、英陽、土城、長端と通って、臨時江を渡って南に入り、麻浦を経て、ソウルへと向かった。
十二月二十七日、雪の降りしきるなか凍った漢江を滑り転びながら渡って、出発してから二十四日目に私たち三人は、夢に見たソウルへ辿りついた。
私たちはまず、永登浦区黒石洞にある郭という人の自宅を訪ねた。しかし、文さんの昔の親友だった郭という人は、すでに釜山の方へ避難してしまい、そこは空き家になっていた。この家は二階建ての洋風の家で、家財道具がそのまま置いてあった。仕方なく私たちは、この空き家でしばらく過ごすことにした。
ソウルは文さんにとって、学生時代から暮らし、信仰的な面でもいろんなことを体験してきた第二の故郷だった。そこで文さんは、日本留学を終えて帰国後しばらく下宿をしていた、李寄鳳というおばさんの所を訪ねていった。しかし、なぜかさほど喜んではくれなかったようだった。そのあとも、何人か昔の親友を訪ねていったが、文さんの様子を見て変に思ったのか、あるいは私たちの様子が変だったのかもしれないが、あまり親切にはしてくれなかった。
ところでこの頃、ソウル市民は国民防衛軍の要員に駆り出されていた。私はまだ足が不自由だったのでひっかからなかったが、文さんと元弼の二人は無条件で引っ張られてしまった。三人で死線を乗り越え、平壌からやっとソウルへ着いたのに、これはどういうことなんだろう。私だけ一人残され、今後のことが心配だが、どうすることもできなかった。
私にとってソウルは、慣れない土地で、知り合いも一人もいない所だ。しかも戦争中である。
文さんが訪ねていっても親切にしてくれなかった人たちを、仮りに私が訪ねたとしても、私になど同情してくれるはずがない。これから私はどうすればいいのか、いくら考えても何も浮かばなかった。文さんだけを信じて待つしかなかった。
幸いにも文さんと元弼は、国民防衛軍の身体検査で不合格になって帰され、三人はまた、黒石洞の郭さんの自宅で一緒に暮らすことになった。
明けて一九五一年一月二日、ソウル全域に退去命令が出された。共産軍が近くまで南下して来たのだ。私たちはまた避難の旅に出なければならない。今度の目的地は釜山だった。
いままで検問を受けたりしたときには、まず最初に、証明書の提示を要求された。そのことを思い出して、私は近くの治安隊を訪ねた。柳鴻という治安隊の隊長にその間の事情を話して、私たちに「避難民証明書」を一通ずつ作ってくれるように要請したら、親切に証明書を発行してくれただけではなく、「気をつけていってらっしゃい」と慰労の言葉までかけてくれた。そのときの気持ちは、いまだに忘れることができない。
平壌から準備してきた金も全部なくなってしまったので、私たちは仕方なく、郭さんの自宅に残されていた洋服や金になりそうなものを自転車の後ろに乗せて、ソウルを出発した。たとえそのまま残しておいたとしても、人民軍や中国軍がやってきたら、何も残らないことは明白だった。
事実、ソウルは一月四日、再び共産軍に制圧されてしまった。
63頁
ソウルから釜山ヘ
第二の避難行
私たちは一月の三日、今度は釜山に向かって、五百キロの避難の旅に出た。二回目の避難である(いわゆる韓国史の「一・四後退」のとき)。
あいかわらず私は自転車に乗って、ただ押されていくありさまだったが、自由を求めていく希望の道には違いなかった。ソウルを出発してから、私たちは釜山まで京釜線(ソウルから釜山までの鉄道)に沿っていかないで、中央線に沿っていくことにした。その理由は、私の叔父になる鄭基琇さんが堤川という所に住んでおり、そこに寄っていけば、いろいろ助けてもらえると思ったからだ。
まず城南を経て、利川に向かった。今回は平壌からソウルまでの避難とは違い、見知らぬ避難民たちが列を作っていたり、また山になって動いているのでもなかった。同じ村に住んでいる人たちとか、家族同士が一緒に移動していくのであった。
日が暮れて暗くなると、近くの村に入った。村にはほとんど人が住んでおり、空き家が見つからなかった。そこで、ある家に行き一晩休ませてほしいと頼むと、快く受け入れてくれ、部屋を借りて休むことができた。空いている部屋がないときには、台所や物置などで休ませてもらった。休む場所が確保できれば、あとは持っていた米で食事を作り、食べて寝るだけだった。
第二の避難では、前の経験があったので気持ちにも多少余裕があり、そんなにあわてることなく、のんびり行くことができた。日が暮れないうちに早めに村に入り、早めに宿を確保するのが、上手なやり方なのだ。
手持ちの米がなくなってしまったので、近くの小さな村に寄った。ところが、この村の人たちは避難してしまったのか、商店はほとんど閉まっている。しかし私たちは、どうしても米を手に入れなければならなかった。そこで、その小さな村の中にあった大きな家を訪ね、郭さんの家から持ってきた洋服を一枚出して、家にいたおばあさんに渡し、こちらの事情を説明した。七十を過ぎたくらいの気のよさそうなおばあさんは、私たちがかわいそうに見えたのか、それとも洋服がほしかっただけなのか、米びつを開けて白い米を一升くらいくれた。
長胡院、原州を経て堤川へ。助けをあてにして捜しあてた叔父の家は、すでに避難して空き家になっていた。がっかりしながらも先へ進み、島嶺の頂上に到着したとき、UN軍の憲兵に「避難民は道路を使ってはいけない」と止められた。そうなるとこれからは歩きにくい山道を行くしかないが、その頃には私の足もほとんど治りかけていたので、山道でも何とか自力で歩いていけるだろうと思っていた。すると突然、UN軍の憲兵が文さんと元弼を強制的に連れ去ってしまった。ここで三回目の離別になるのかと、私はとても不安になった。最初は北から避難するときで、保安隊に連行された。次はソウルで、国民防衛軍によって連れていかれた。そして今回も、また一人残されてしまった。
こんなところに一人残されても、どうすればいいのかわからない。とても心配だったが、しばらくしたら二人は帰って来た。UN軍の軍用車のために作業をさせられたということだった。
これからは下り道だったので、私一人でも歩いていけそうだった。
「ここからは杖を捨て、歩いていこう」と文さんが言った。
二か月近くも杖に頼り、自転車に乗ったり降りたりしていたので、まだ自信はなかったのだが、思い切って杖を捨ててみたら、杖がなくても歩けたのである。こうしてその後の道を、私は一人で歩いていくことができた。丹陽、聞慶、杏材、豊山、安東、義城と避難行は続いた。
慶州での別れ 66
慶州に到着したのは夕方だった。町には避難民があふれており、空いている部屋はなかなか見つからなかった。私たちは方々をさまよって、やっと市内の路西里で泊まれそうな家を見つけた。玄関のドアを板で×型に打ちつけている家で、その家を訪ねたら三十歳くらいの人が出てきた。
私たちが訪れた理由を聞かれたので、「板でドアが閉じてあるので、誰も住んでいないようだったから、一晩休ませてもらおうと思った」
と話したら、中へ入れてくれた。家の中の様子を見たら、板で何かを作っている工場のようだった。家の主人の説明では、「御膳」を作っていたのだが、戦争のために職人たちが皆、故郷に帰ってしまったので、工場を閉鎖するしかなかったのだという。
部屋を借りたあと、元弼は夕食の材料を仕入れるため市場に出かけていった。漁港のある浦項が近かったので、イカを三バイ買ってきてお粥を作った。元弼が部屋を貸してくれた主人のとこにお粥を一杯持っていったら、あとで奥さんが「このお粥はどうやって作ったの?」と聞きにきた。元弼が説明すると、奥さんは笑いながら、「イカでお粥を作るときは、スミをとってから料理するのよ。そのまましたでしょう」。私たちは暗い所で食べたので、気づかずにおいしく食べてしまったが、奥さんが持ってきたお粥を見ると、なるほどまっ黒だった。それを食べたかと思うと、私たちはお互いに笑ってしまった。
この家の主人は「北の黄海道が故郷だが、自分は小さいときに慶州にやってきて、生活のために御膳を作るようになった」という。親は今も北にいて、自分の家族だけがこちらに住んでいるということだった。彼の名前は張萬榮といった。
三日間この家で休んだ。食事はもちろん自分たちで作って食べていた。でも、避難民があふれて混乱している所に、長い間いることはできない。主人に「私たちは今日、釜山の方へ行きます」とあいさつしたら、「若い二人は行っても大丈夫だろうが……」と彼は、私を指差して言った。
「あなたは一番年上のようで、身体も弱っているようだ。釜山へ行っても避難民でいっぱいのはずだから、二人だけ先に行って、落ち着いてからあなたも行けばいい」
ここまで文さんと元弼と一緒に死線を越えてきたので、私は、
「いや、私も釜山へ行きます」
と言ったが、文さんは「この主人の気持ちもありがたい」と言って、
「正華、あなたはここにいながら、もう少し待ちなさい。私たちが釜山に行って落ち着いたら連絡するから、そのときまた一緒になって、大きな仕事をすることにしよう」
こうして、私は慶州の張萬榮の家に残り、文さんと元弼は釜山に出発することになった。そのときの私の心境はとても複雑だった。避難の途中、文さんと一緒に死線を何回も乗り越えてきたのに、そして神の意志のためにやろうとする偉大な仕事のためここまで来たのに……。一人で残される私の気持ちは悲しくて、一緒に行きたい気持ちでいっぱいだったが、避難は一人でも少ない方が楽だと思い、しばらくの別離を受け入れることにした。
あとで文さんが慶州へ来たときに聞いたのだが、このときは蔚山まで歩いていき、蔚山から初めて汽車に乗れたという。汽車は汽車だったが、貨物車両の屋根まで人が乗っている状況で、どうにか煙突のあたりに乗れて、釜山の草梁駅に辿りついたそうだ。
その日は、一九五一年一月二十日だったということである。
生活に追われた文の来訪 68
私は一人慶州に残り、張萬榮の家で居候していた。四月になって気候も暖かくなった。居候も長くなるので、何とかして飯代くらいは払わなくてはと思い、私はある日、主人と話した。
「戦争中は作ってもあまり売れないから、工場を閉鎖している」ということだったが、
「御膳さえ作ってくれれば、私が自転車に乗せ、市場で売ってくるから、やってみよう」
と私が勧めたら、主人もその気になった。そして、前から工場で働いていた子と、居候していた避難民の男と主人の三人で、御膳を作り始めた。私は一回に二十個ずつ自転車に乗せ、浦項に行ったり、永川に行ったり、また蔚山にも行った。慣れない商売だったが、持っていった御膳はどうにか売れたので、その代金を主人に渡した。
慶州の周囲には四方に市場があった。永川も、蔚山も、浦項も、彦陽も、甘浦も、慶州から二、三十キロの所にあったので、五日ごとに市がたつそれぞれの市場に、毎日のように御膳を運んでは売っていた。
また夕方になると、その家の中学校に通っている子どもの家庭教師もやったので、居候している間の飯代くらいは十分に稼いだ計算になる。
こうして過ごしていたところ、その翌年の三月七日、突然、待ちに待った文さんが釜山から来てくれた。その嬉しさは言葉で表わせないほどだった。けれども軍用の毛布一枚で工場に寝泊まりしていた私としては、文さんを歓迎する術がない。主人がお金を出してくれて夕食だけは接待できたが、夜は木屑だらけの部屋に泊ってもらうしかなかった。文さんはその間、釜山での出来事や今後の計画について話してくれた。夢のような話ばかりだった。まるで何十年かぶりの再会ように、夜遅くまで二人で話し合った。
あくる日、文さんは「今日、また釜山に帰る」と言った。私の気持ちとしては、ここに部屋がもう一つあれば、ここで経済的な基盤を作れるような活動をして、文さんと一緒にいたい気持ちだったが、まだ状況が悪いので仕方なかった。
ちょうどその日は蔚山の方で市があったので、文さんと一緒に汽車で行くことにした。午前中、私が市場で御膳を売っているのを文さんは見ていた。昼食を食べたあと、文さんは汽車で釜山に向かった。御膳がたくさん売れたらお小遣いでも差し上げようと思っていたが、よりによってその日は、なぜかほとんど売れなかった。
慶州で別れてから一年ぶりの再会だったが、文さんを見送って帰ってから私は、本当に考え込んでしまった。何か商売をして資金を用意し、釜山へ行って、文さんとともに偉大な仕事の達成に努めなければならない、ということばかり考えていた。
文さんの話によると、元弼は食堂で仕事をしており、文さん自身は日本の工業学校で一緒に留学していた同窓生の家に居候している、ということだった。さぞかし、居心地が悪いだろうと思う(実はこのとき、彼は私の所で生活ができれば――と様子を見に来たのだった)。
どうすれば一日でも早く経済的基盤ができるようになるかを、私はずっと考えていた。毎日のように御膳を運び、市場で売るのが私の仕事になっている。こういう仕事でも一所懸命がんばっていれば、チャンスがやってくるだろうと希望を持ち、ここで待つしかないのか。いっそのこと釜山へ行った方がいいかもしれないと思ったが、まだ避難民でいっぱいの釜山へ行っても仕方ないのではと考え、もう少し慶州にいることにした。
平壌から来た玉相賢との再会 71
共産軍によって二年前の一月四日に再び陥落したソウルは、ちょうど二か月後の三月四日、UN軍が奪回していた。ソウルではこの当時、一進一退ながらようやく戦火も下火になり、休戦協定の準備が進められていた。しかし、民間人の死傷者だけで南北合わせて二百万人以上、離散家族も一千万人を越えるといわれ、国民の間に不安や不幸の影が色濃く充満していた。
そんな一九五三年の春。釜山からあの玉相賢おばさんが慶州に私を訪ねて来て、久しぶりに再会した。平壌から避難するときに別れてしまい、お互いに消息不明だったが、こうして会えて本当にうれしかった。
玉相賢からは、彼女の避難の話や釜山の文さんの安否などを聞いた――文さんが食口(信者)たちの育成にがんばっていること、原理を本にするための原稿を書き終えたこと。興南監獄のときに話していた原理を整理して出版しなければならないと、いつも文さんが話していたことを思い出して、こんなにたいへんな避難生活のなか、いよいよ書きあげられたかと感激した。早急に経済的な基盤を作り、原理を出版して全国に配布し、伝道していかなければならないと思った。
玉相賢は、長男が軍人用のトラックを持ってきたおかげで、家族全員が無事に南の方に来れたそうだ。落ち着いたら釜山で一緒に仕事しよう、一日も早く、経済的な基盤ができるように努力しよう、文さんと一緒に六千年前の神様の意志のために偉大な仕事をするときが、もうすぐやってくるだろう、などと熱心に話した。元弼は今、米軍の部隊で仕事をしているそうだ。凡一洞に教会を作って、新しく入信した食口たちが原理を聞きに集まるようになり、平壌にいた食口たちも釜山に来ているという。教会の近所に住んでいる人たちも、文さんの話を聞きに来ているそうだ。
玉相賢は一晩一緒に過ごして、次の日釜山へ帰っていった。
それからしばらくして、李耀翰という牧師が私を訪ねてきた。釜山にいる文さんがよこしたということだった。部屋に案内して話を聞くと、
「新しい食口たちがたくさん集まり、原理の話を聞くようになっているので、朴正華さんも先生がいらっしゃる釜山に至急来てほしい」
ということだった。みんなが力を合わせ、神のための偉大な仕事に前進する時期がいよいよ来たと、胸がいっぱいになった。
その次の日、李牧師は釜山に帰った。私もすぐに釜山へ行くと文さんに伝えるよう頼んでから、一人で考えた。
あの興南監獄で、文さんが空叺の上に座って目をつぶったまま、将来の世界を変化させる理想、すなわち「円和園理想」の世界を実現しなければならないと、私に言われたことを思い出した。そのときの情景が浮かんでは消えた。あこがれの世界が一日でも早く来てほしかった。罪悪のない世界、そして嫉妬、陰謀、裏切り、戦争などない世界。その理想世界の会員にさえなれば、労働は趣味として一日三時間だけすればよい。世界のどの国へも行けて、会員の家に行けば、泊まり、食べて、使うことは好き放題できる。黒、白、黄色の皮膚に関係なく、お互いに親子兄弟のように、すべてのことができる。もらうよりは、あげることを喜ぶ世界。他人を責めることはせず、尊敬を受けるよりは尊敬することを喜ぶ世界。この理想世界が地球の隅々まで広まって、私たちはどの国でも気持ちが通じ合うことができる。
この世界が近い将来、いま釜山で苦労している「文龍明先生」によって達成されることを考えたら、感激するばかりだ。
私は一刻でも早く、釜山に行かなければならなかった。